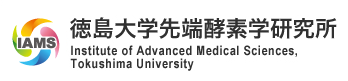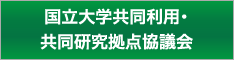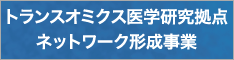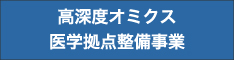所長挨拶

徳島大学先端酵素学研究所は、1961年に設立された医学部附属酵素研究施設をルーツとしており、2016年に疾患酵素学研究センター、疾患プロテオゲノム研究センター、藤井節郎記念医科学センター、糖尿病臨床・研究開発センターの4つのセンターが統合されて設立されました。現在の本研究所は、生体反応の触媒としての構造・機能を探る従来の酵素学を基盤に、オミクス解析やゲノム編集などの最新技術を駆使して、ゲノムから個体レベルに至る生命情報の本質的・統合的な理解を目指した最先端の医科学研究を推進しています。
本研究所は、初代所長の高浜洋介教授の先導のもと、酵素学研究の伝統と先端的な基礎医科学研究が融合した附置研究所としてスタートしました。その後、第2代所長の佐々木卓也研究担当理事により、徳島県最大の健康課題である糖尿病をはじめとした生活習慣病・がん・免疫疾患などを「慢性炎症」という共通の病態基盤で捉えた研究領域が重点分野として確立されました。そして第3代所長の片桐豊雅教授の時には、文部科学省の共同利用・共同研究拠点の1つである「酵素学研究拠点」として再認定を受け、また「高深度オミクス医学研究拠点整備事業」および「関西共創の場」を活用することによって研究ネットワークが拡充されました。さらに、第4代所長の松久宗英先生のもと、優れた組織運営の成果が認められて共同利用・共同研究拠点として高い評価を得るなど、研究所は着実に発展を遂げてきました。
現在、徳島大学は「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業」に採択され、光工学・慢性炎症研究・栄養学・情報科学の融合による学際的研究を推進し、超高齢化社会の課題解決に挑戦することになりました。その一環として、Institute of Photonics and Human Health Frontier (IPHF)が創設され、本研究所もこの枠組みに参画する予定です。これにより、本研究所に所属する研究者が国際的に高く評価される研究成果を発信し続けることに加え、次世代を担う若手研究者にとって魅力ある研究環境を提供することが求められています。国内外の先駆的な研究者との連携を深め、研究機能の強化と優れた人材の育成と集積に努めてまいります。本研究所への温かいご支援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
先端酵素学研究所 所長
小迫 英尊
沿革
| 昭和36年4月1日 | 文部省令第7号国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令により、徳島大学医学部附属酵素研究施設として設置 |
| 昭和62年5月21日 | 文部省令第17号国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令により、徳島大学医学部附属酵素研究施設及び医学部附属海洋生物実験所を包括して、徳島大学酵素科学研究センターを設置 |
| 平成9年4月1日 | 文部省令第13号国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令により、10年期限の研究機関として、酵素科学研究センターを改組して、分子酵素学研究センターを設置 |
| 平成19年4月1日 | 10年期限の研究機関として、分子酵素学研究センターを改組して、疾患酵素学研究センターを設置 |
| 平成22年4月1日 | 共同利用・共同研究酵素学研究拠点に認定 |
| 平成28年4月1日 | 疾患酵素学研究センター及び疾患プロテオゲノム研究センターを改組して、先端酵素学研究所を設置するとともに藤井節郎記念医科学センター及び糖尿病臨床・研究開発センターを同研究所の附属施設とする。 |
| 平成28年4月1日 | 共同利用・共同研究酵素学研究拠点に認定 |